| タイトル(かな) | ふぁいなるふぁんたじー16 |
| ハード | PS5 |
| 発売日 | 2023年6月22日 |
| 点数 | 79点(良作) |
| 総評 | ・「見せる」「魅せる」に特化した映像作品 ・圧倒的な映像美 ・こだわりを押し出しすぎてマイナス面も |
序文
ファイナルファンタジー16(FF16)は、2016年発売の「15」以来、約7年ぶりとなるFFシリーズのナンバリングタイトル。発売前の公式の宣伝映像では「画面が暗い」といったネガティブな意見がインターネット上で散見された本作だが、蓋を開けてみれば楽しむことができた。
このあたりの「事前の評判が悪いが、いざ発売すれば面白かった」というのはFF7リメイクでも通った道なのだが、こと本作については、そもそも詳細なレビューが少ないという声もインターネット上で散見される。
そのような声が見られる理由として、「FFブランドの注目度の高さ」というのも挙げられるだろうが、個人的に感じたのは、本作は意外とレビューしにくいゲームであったということだ。作品としては凝っているが、ゲーム性はシンプルなので、感想もまたシンプルになりがちで、その結果「詳細なレビュー」が生まれにくい環境にあるのではないかと感じている。
本レビューでは、そんなファイナルファンタジー16(FF16)の面白かった点、残念だった点につき、忖度なしにレビューしていく。
なお、重大なネタバレ箇所については可能な限り非表示にしているが、記事の閲覧の際は十分に注意いただきたい。
ファイナルファンタジー16(FF16)は「映像作品」に近い
プレイした方の大半が感じたことであろうが、本作は、ゲームというよりも「観る」作品としての性格が強い。映像作品に片足を突っ込んでいると言っても良いだろう。
基本的なゲーム進行は、マーカーからファストトラベルしてイベントシーン閲覧、少し移動してイベントシーン閲覧、戦闘が入ってイベントシーン閲覧…の繰り返しである。
各フィールドそのものはそれなりの広さはあるが、オープンワールドゲームではないため、いわゆる探索要素はほとんど無い。したがって、探索をしながらマップを埋めていくといったゲーム体験はあまりない。
戦闘はアクション系であるが、難易度は低めで、サポートアイテムやシステムも充実しており、まず詰むことはない。また、ボス戦闘ではプレイヤーの操作を介さない(あるいは、ごく簡単な操作のみの)シネマティックな演出が多用されており、戦闘についても「魅せ」を重視した作りになっている。
つまり、本作は物語を楽しむことが主要なゲーム体験であり、それに付随する移動や戦闘といった諸要素はスパイスに過ぎない。
それが良いか悪いかについてはここでは一旦述べない。とにかく、そういう作りになっているゲームであるということを最初に述べておく。
シナリオ:掴みは最高だが中盤以降にかけて納得感に欠ける
導入は見事の一言
シナリオは全体的に暗めかつシリアスな雰囲気で進行していく。特に再序盤(体験版の範囲)の引き込みは見事の一言で、主人公クライヴの少年時代の悲劇を追体験することで、プレイヤーを一気に物語に入り込ませてくれる。その後訪れるであろう復讐劇の予感を胸に、プレイヤーはゲームを進めていくことになる。掴みのワクワク感はバッチリで、120点の出来であったように思う。
中盤以降、徐々に様子が変わってくる
さて、そんなわけで最高の滑り出しを(体験版で)迎えた本作だが、中盤以降徐々に違和感を覚えてしまった。以下、ネタバレ要素が強いため閲覧の際は注意。
シナリオ部分を総括すれば、筆者は序盤の雰囲気が大好きだったので、中盤以降は序盤ほどの盛り上がり感はなかったというのが正直な感想だ。
ただし、個々のシーンの演出面は見応えがあり心揺さぶられるものがあるので、細けえこたあいいんだよ!感で力押しに楽しむことができるため、全体で見ればかなり楽しめた。
グラフィック:圧倒的な映像美
グラフィックは本当に凄かった。これまでプレイしたJRPGの中でも一番ではなかろうか。物語への没入感を何段階も引き上げてくれる素晴らしい出来だった。
特に召喚獣バトルについてはド派手で、語彙力不足により残念ながら上手に説明できないのだが、とにかく良かった。ボス戦で挟まれるシネマティックな演出は必見である。
また、巷でよく言われるリップシンク(キャラの口パクが日本語ボイスと合っていない)問題については、正直筆者はあまり気にならなかった。割と多方面で言われているので、人によっては気になるのかもしれない。
フィールド:探索要素は少ない
各フィールドマップもかなり作りこまれており、制作陣の気合いが伺える。ただ、本作はオープンワールドゲームではないので、フィールドそのものを探索して何かを発見するという要素はかなり控えめであった。
隅々まで探索しても何かが見つかるということはほぼ無いので、基本的にフィールドは通り道である。クエストの目的地やリスキーモブの出現地点になることはあるが、探索したことにより新しい発見があることは少ない。
せっかくの国内屈指の美麗グラフィックであるにも関わらず、探索要素が少ないことによりフィールドを隅々まで巡るような動機づけがなされていない点については残念である。
ただ、本作にさらに探索要素を追加してしまうと、色々散らかりそうな気もするので、あえて無くしてストーリーに集中させる、という選択は正解なのかもしれない。
移動:ストレスが大きい
移動面についてはいくつか言及していきたい。良い点、悪い点それぞれあった。
(良い点)爆速ロード時間
ハード性能の高さか、さすがのロード時間の短さであった。ファストトラベルのあるゲームでは、ファストトラベル時のロード時間の長短がひとつの評価指標となるが、本作はごく短時間の暗転を挟むのみで、スムーズにエリアジャンプができた。
また、それ以外にも、フィールドから戦闘への入りや、ボス戦におけるシネマティックな演出への移行などがシームレスに行われたりなど、ロード面で気になる瞬間はほぼ無かった。
強いて言えば、メニュー画面でのLRによる各メニュー切り替えがややモタつくくらいか。
(悪い点)癖のあるダッシュと街中の移動速度
移動面では、妙なところでリアル感を出そうとしている印象を感じ、それがマイナスに働いていた。
まず、ダッシュボタンが存在せず、フィールドで一定時間走っていると自動でダッシュに切り替わる方式となっている。ダッシュ始動までにやたら時間がかかるのでシンプルに面倒。その割にチョコボ騎乗時はR2ボタンですぐダッシュできるので、意図がよくわからない。
また、街の中ではダッシュをすることができず、移動速度が遅い。街中でチョコボに乗れないのはわかるが、ダッシュすらできなくなる。確かに街中で全速力で走るのは現実世界においては不自然かもしれないが、これはゲームである。本作は街や拠点が広い上に、拠点内ワープなどもないので、かなり負荷がかかる。
ついでに細かいことを言うならば、チョコボ騎乗時に視界がクライヴの傾きに合わせて左右に揺れる点が気になる。このせいで、騎乗後に向いている向きがわかりにくく、微妙に混乱することが何度かあった。
(悪い点)ミニマップ削除は正しかったのか?
また、本作は「あえて」ミニマップを実装していない。これは、発売前に行われた体験版フィードバック動画で名言されている。その理由は、要約すると、ミニマップを実装するとただミニマップを見ながら移動するだけのゲームとなり、没入感が落ちるからというものだ。
一理あるようにも思えるが、筆者としては以下の理由で、やはりミニマップが欲しかった。
- ミニマップを見ない代わりに、こまめにタッチパッドによる全体マップを見る機会が増えるだけである。押すたびに画面が切り替わるので、むしろこっちの方が没入感が落ちる。
- 拠点となるクライヴの隠れ家がやたら入り組んでおり、慣れるまでは普通に迷う。
- ミニマップのないオープンワールドゲームは確かに多数あるが、それらのゲームは、崖や段差などに強いので、大まかな方向を全体マップで見て、そっちの方向にひたすら進む ということができるのだが、本作ではちょっとした崖を飛び降りたりすることもできないので、そういった方法が取りづらい。湿地帯など、どこを通れるかわからず、いわゆる「見えない壁」がそこら中にあるため、マップによる地形確認の手間が多く発生する。
総じて、移動面では読み込み時間の短さは特筆すべき良さがあるが、それ以外での全体設計が良くないと感じた。「リアルにしたい」「景色を見て欲しい」といった開発側のこだわりや願いが、マイナス面に働いてしまっている印象だ。
バトル:オーソドックスで奥行きが少ないアクション。ただし、演出面は凝っており面白い
バトル面は、前述のシネマティックパート(バトルからシームレスに切り替わる映画のような演出)については迫力がありアガるのだが、それ以外の通常の戦闘においては特筆すべき点は少ない。だいたいどこかで見たようなシステムだ。
複数の召喚獣を切り替えるモードチェンジは、「龍が如く0」などで見られるスタイルチェンジに近しいものだし、ウィルゲージの削りによるテイクダウンシステムなども、「SEKIRO」の体幹削りをはじめ、様々なアクションゲームで類似のシステムが見られる。よく言えばとっつきやすいオーソドックスなアクションRPGだが、悪く言えば面白味のないシステムだ。
ただし、よく叩かれがちな属性相性を無くした点については、むしろ英断だったと感じている。戦闘中に召喚獣やアビリティを付け替えできない本作では、仮に属性相性があった場合、ボス戦における「予習」が必須となり、ゲームとしての面白さを著しく損なうからだ。その経験は、FF7リメイクで味わってきた。
また、バトルシステムそのものは斬新さに欠けるとはいえ、バトル中のエフェクトの美しさやシネマティックアクションに代表される演出面の迫力、操作性の良さなどから、チープな感じはせず、爽快感もあり、かなり楽しむことができた。
ただ、全体的な難易度の低さも相まって、慣れてくると単調さは否めない。特に雑魚戦は完全に作業になりがちなので、退屈に感じることも多くあるだろう。
召喚獣操作時は、与ダメージが文字通り桁違いとなるので、異次元レベルのバトルをしている感も良かった。リスキーモブは人間状態でしか戦わないので、この手のゲームにありがちな「ラスボスよりその辺の強敵の方が強い」問題も生じないので、世界観を守れている点も◎。
総評
ファイナルファンタジー16(FF16)は、難易度やゲーム性を削り落として、詰ませることなく、プレイヤーにクリアさせてシナリオ・演出を楽しませることに極限まで集中したゲームであった。すなわち、ゲーム要素のある映像作品なのである。したがって、シナリオ部分が楽しめるかどうかが本作の評価軸なのだが、全体的にとても楽しめた一方で、やはりマザークリスタル破壊周りの描写の勿体なさや、前半と後半でがらりと変わるストーリーの雰囲気がやや気になるところであった。
あとはやはり移動面。本作の移動面の制限は、ゲームとしての楽しさを生み出しているというよりも、制作側のこだわりや見せたいところを押し付けられているように感じてしまったので、その点はややマイナス。
長短ひっくるめた全体評価としては、FFのナンバリングに相応しい大作であったと思う。未プレイの方にはお勧めできるし、プレイして損のないゲームである。
DLCにも期待したい。
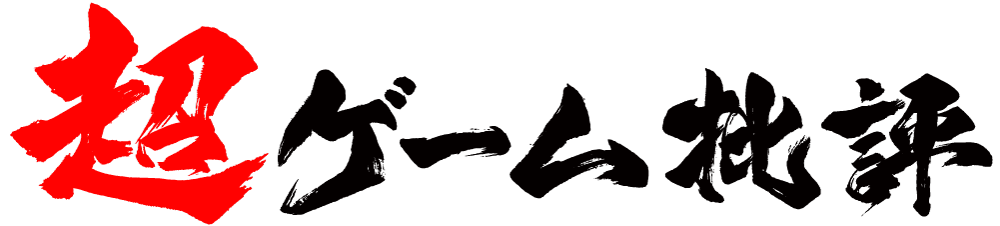
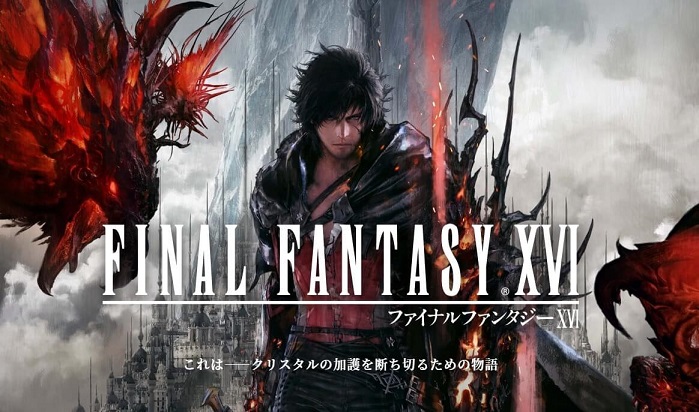

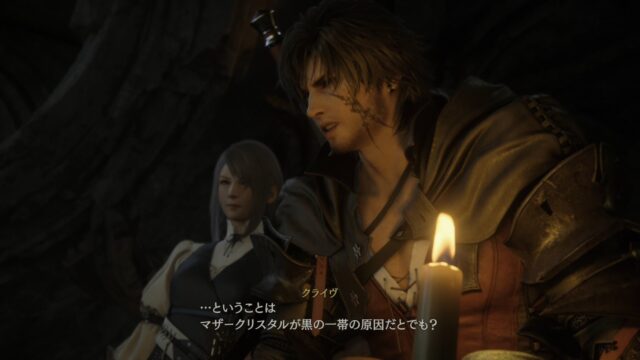

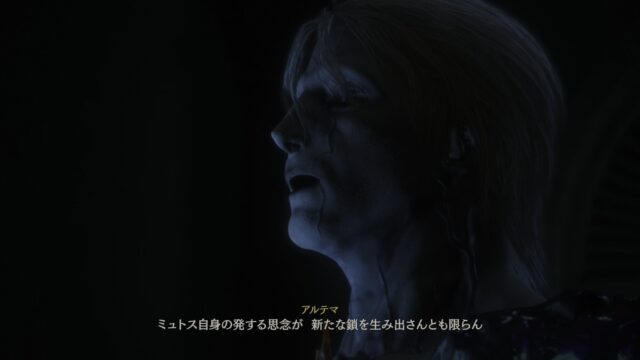












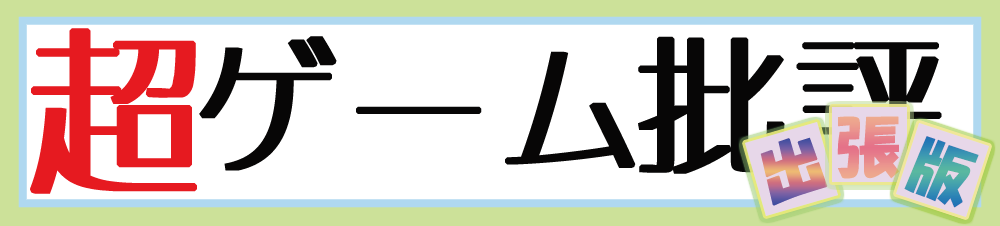
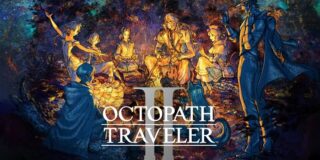



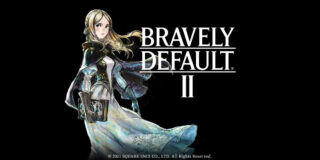
こちらでは初めまして。FF16はDLC第二弾までクリアしたのですが、管理人さんがおっしゃる様に王道の「世界を守る系ファンタジー」になっていくのが不自然だったので、シナリオと探索面ではマイナス
評価をされても仕方ないと自分も思います。
DLC第二弾で伝説のリ〇ァイア〇ンが出てくるんですけれど、
それも意外性を狙ったのか、同行してくれるキャラは終始
良い人であり、そして説明不足のシナリオ展開で終わりました。
某カードゲームアニメ作品でも言われた「全部〇〇って奴が
悪いんだよ!!」を繰り返すようなアルテマが黒幕だった
というオチを強化したい思惑が節々に感じられました。
どうすれば良かったかなと素人である自分が思ったのは、
Fallout4を参考にして、クライヴが各勢力に所属することを
選べるようにして、最終的にアルテマを倒すようにすること。
Fallout4は主人公がアメリカの様々な勢力と出会い、最終的に
自分の息子か好きな勢力のルートを選び、EDも変わります。
ゲームとCGアニメの違いって「選択次第で変わる主人公の
結末」だと思うんですよ。CGアニメだとどうしても監督が
作った一本道のシナリオに従わないといけない。でもゲームは
プレイヤーによって選んだ物語を楽しむことができると思います。
例えばザンブレグの兵士として生きていたクライヴの前に、
ジルが現れます。ここでジルを救ってザンブレグから逃げる
ルートとそのままザンブレグに残り、ディオンやジョシュアと
共にザンブレグの闇を変えていくルートを選べるようにすれば
FF16はもっと面白くできたと思います。ザンブレグ視点でなぜ
戦争をしているのか、ザンブレグ人は一体何を考えているのかを
知ることもできます。一方、物語でベネディクタから誘われて
そこでシドを裏切ってバルバナスと一緒に行動するルートや
タイタンを持つダルメキアや鉄王国で傭兵として生きる道を
選べるようにして、最終的にどの勢力でアルテマを倒すのかを
プレイヤーに選ばせたら、マルチエンディングが楽しめるように
する。そうすればFF16の「やらされている感」は減り、2周目も
やろうかなと思うんですよね。結局2周目やDLCやろうが結末は
初見プレイと全く同じなら、そりゃ飽きる人は出てきますよ。
各勢力を自由に選べるようにすれば、それこそFFスタッフが
やりたかったゲームオブスローンズのような各勢力の思惑を
プレイヤーに説明できるし、バルバナスルートで人類滅亡を
やるクライヴ達を止めるジョシュア達とのバトルなどを見る
こともできます。このようにゲームだからこそ、様々な展開を
楽しめるようにしたら、FF16はもっと評価上がったと思いました。
長文駄文で申し訳ありません。
追記
バルバナスはアルテマの傀儡だからアルテマを倒すのは
道理に合わないだろうと思うかもしれませんが、この
ルートではクライヴの自我が強すぎて、アルテマの
代わりに世界滅亡して新世界をバルバナスと共に目指す
展開になります。バルバナスは途中からクライヴに心酔し、
そしてバルバナスの口から彼の過去や世界の歴史について
知れるようなルートにすれば、プレイヤーがFF16の世界に
もっと興味を持つようになれたのではと個人的に思います。
最近ここのブログを知ってFF16にはどんな評価を付けてるんだろう?と思って見てみたんですが自分と似た評価で面白かったです
FF16の評価っていうとFFシリーズないしRPGの中でも最低クラスのksゲーってネットの書き込みが多すぎて、自分としては今まで遊んだゲームの中で№1とまではいかなくとも、少なくとも発売日に買って後悔したレベルでは無いし周回高難易度モードもやるくらいには楽しんだけどな・・・と違和感を抱いていたんですがすっきりしました。
俺もFF13を全クリして、まあ敵硬かったけど面白かったな~とネットで批評サイト見たらボロクソで悲しかったよ
コメントありがとうございます。
最近プレイする側の評価が厳しくというか、悪い評価が目立ちやすくなってしまっている傾向にある気はしています。
十分に面白いゲームだなと私も思いました!